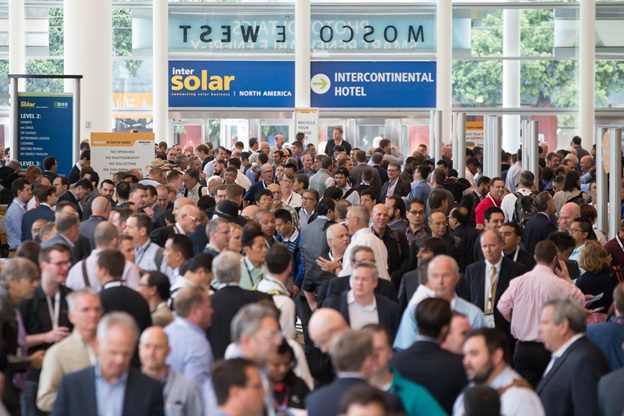総容量は366MWに
先月末、米カリフォルニア州のブラウン州知事は分散型エネルギーを貯蔵するシステムの導入を奨励するプログラムに関し、さらに5年間延長する法律に調印した。このプログラムに対し、追加的に投入される予算は総額8億3000万米ドルに達し、大半の約7億米ドルは家庭・商業用の蓄電池に当てられると予想されている。
このプログラムは「セルフ・ジェン」または「SGIP(Self-Generation Incentive Program)」と呼ばれる、自家発電設備の導入支援補助プログラムで、2000 年夏から2001年にかけて起きたカリフォルニアでの大停電を契機にスタートした。同州は、同プログラムを電力需要と温室効果ガス(GHG)の排出削減策として位置づけている。
補助対象の自家発電設備には、コンバインドサイクル発電、風力発電、燃料電池などが含まれる。ちなみに太陽光発電もこのプログラムに含まれていたが、2007年に太陽光発電用の「California Solar Initiative (CSI)」と呼ばれるプログラムが新設されたのに合わせて、SGIPの補助対象から外れている。分散型エネルギーの貯蔵システムに関しては2008年からSGIP の補助対象になった。
実は同州は昨年5月に2017~19年の3年間を対象に5億6669万ドルの予算を投じたばかりである。この時には、総予算の79%となる4億4819万ドルがエネルギー貯蔵システムに割り当てられた。
ちなみに、現時点での補助金申請データを分析してみると、設備導入済み・補助金交付済みの分散型エネルギー貯蔵は92MWで、支払われた補助金の総額は1億5100万ドルになる。補助金認定済みのエネルギー貯蔵は、導入済みの2倍以上の238MWであるが、支払われる補助金総額は約1億6200万ドルで、市場拡大に合わせて補助金額が引き下げられるのがわかる。ここに、補助金申請済みで認定待ちのエネルギー貯蔵を含めると、総容量は366MWに達し、補助金総額は3億3700万ドルとなる(図1)。
これに近日、法案の可決された7億ドルを加えると、総額10億ドルを超えることになる。...https://tech.nikkeibp.co.jp/dm/atcl/column/15/286991/101600094/?n_cid=nbpnxt_mled_dm